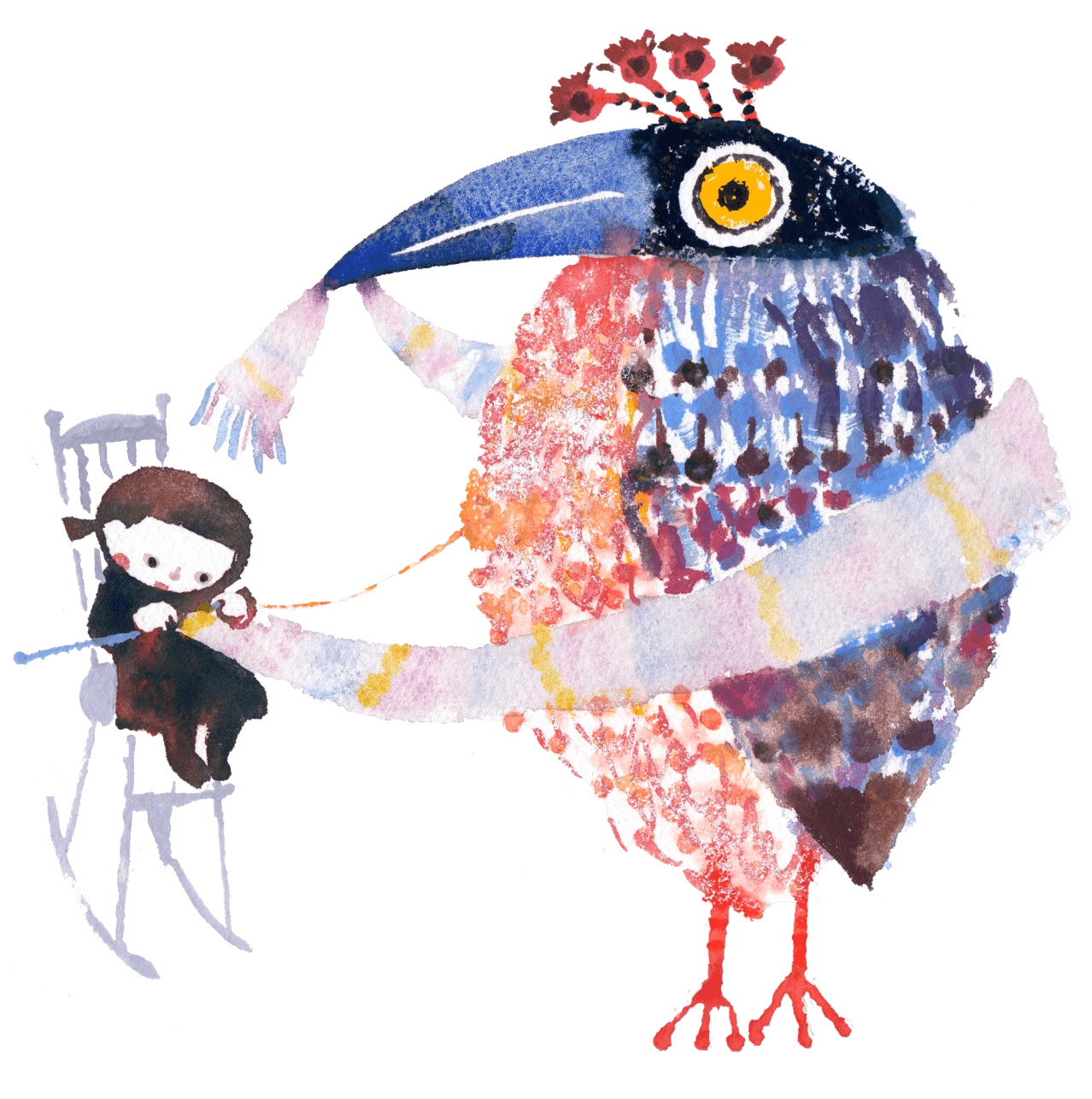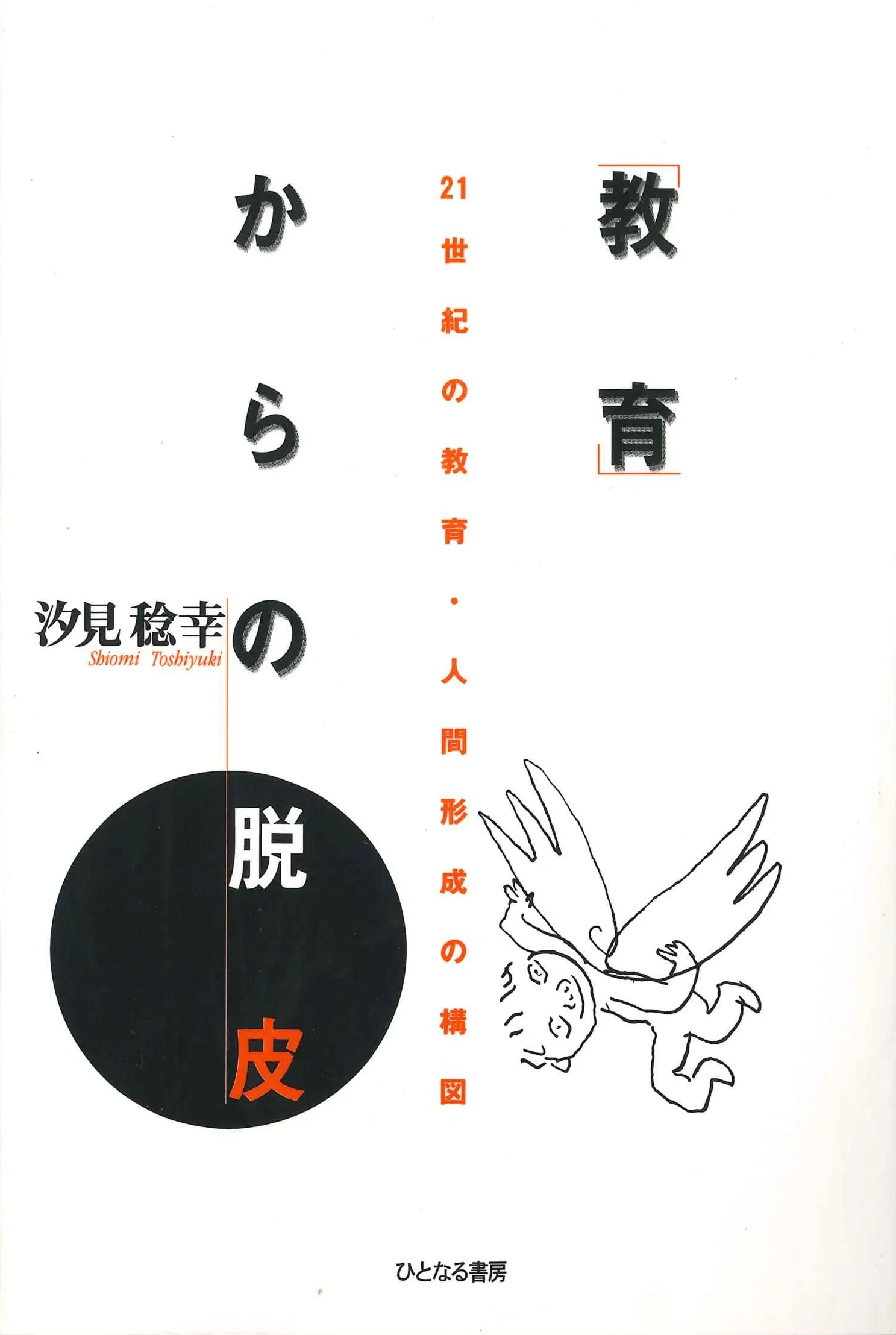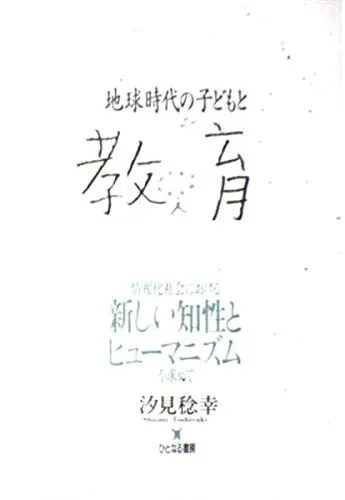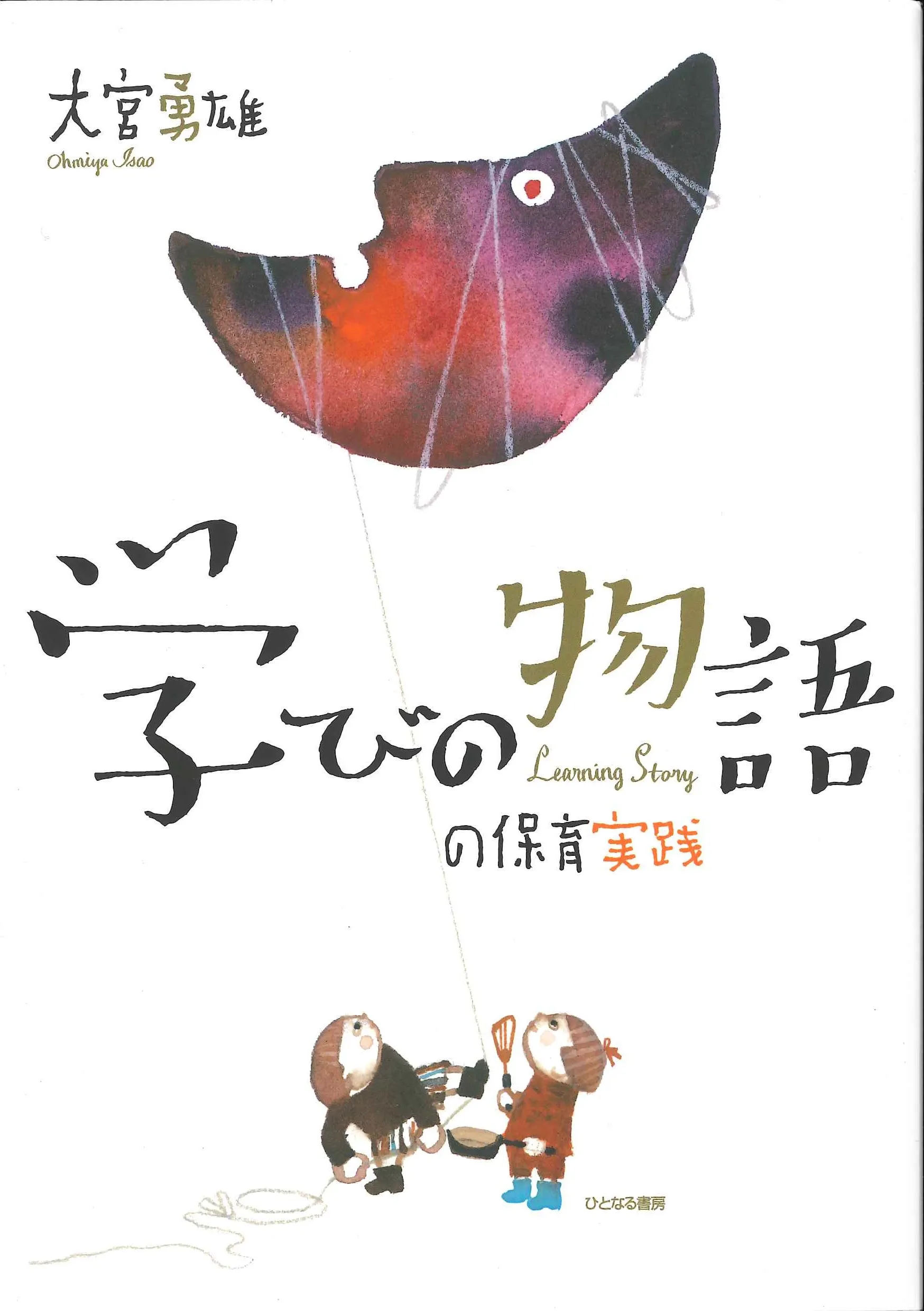暮らしの保育
異年齢保育の先に見えてきたもう一つの保育論
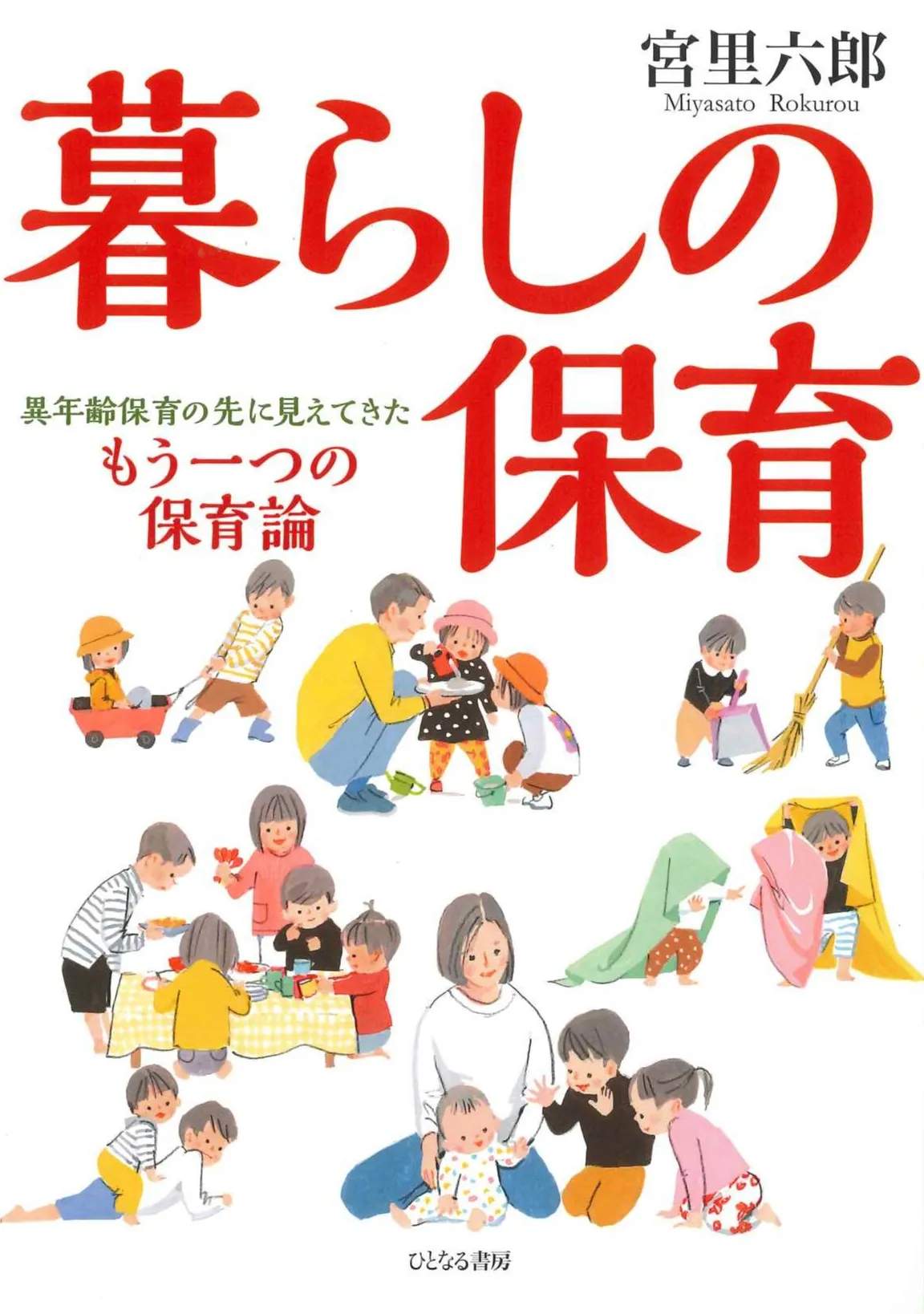
あたりまえの日常を
丁寧におくる
-
発行日
2024年12月17日
-
ISBN
978-4-89464-309-3
-
判型
A5判
-
ページ数
192ページ
-
定価
2,200円(本体2,000円+税)
内容
保育通信2025年2月号に書評掲載(執筆:諏訪保育園園長・島本一男)。くわしくはこちら!
著者を交えたちいさな読書会の様子はこちら。
2025年5月から2026年3月までオンライン読書会毎月開催! くわしくはこちら。
「学校」モデルの年齢別保育とは違う、1歳~5歳の異年齢保育に取り組むと、保育の風景が一変します。見よう見まねで子どもが自ら育とうとする姿や、互いに助け合い育ち合う姿が、あたりまえになります。保育者の子どもを捉える視点や振る舞いも、大きく変わっていきます。何より、園に安心感が満ち、誰にとっても居心地のよい場になります。そこに生まれた保育を、私たちは「暮らしの保育」と名付けました。
目次
序章 異年齢保育新段階
Ⅰ 「暮らしの保育」の風景
Ⅱ 「暮らしの保育」の子どもの育ちと大人のまなざし
Ⅲ 「暮らしの保育」の構えと振る舞い
寄稿1 「暮らしの保育」の夜明け 小山逸子
寄稿2 異年齢保育の背景と年齢別保育との関連 渡邉保博
目次全文
序章 異年齢保育新段階――安心感を土台にした〈おうち〉モデルの「暮らしの保育」
1 異年齢保育新段階そして新時代――量的広がりと質的深まり
2 1〜5歳の異年齢保育の変遷――安心感を土台にした〈おうち〉モデルの「暮らしの保育」
Ⅰ 「暮らしの保育」の風景
第1章 台所と食卓を暮らしの真ん中に――三島奈緒子実践(きたの保育園)から
1 保育室にキッチンがある食の風景――ごはんは各〈おうち〉の炊飯器で炊きます
2 食の原風景――台所の大人は、給食の時間は子どもの食事におつきあいします
3 大皿盛り――自分で決めて他者と分かち合う
4 人生に必要な知恵はすべて食卓で学んだ
5 台所職員の子どもへのまなざし――食の専門家、一味違った子ども好きな大人
6 暮らしを「食」から「衣」や「住」(家事的作業)に広げることも
第2章 暮らしとしての「季節と天気」「ご近所」、人間模様としての「1歳児」――石坂聖子実践(ひまわり保育園)から
1 季節を織り込んだ暮らし
2 ひまわり長屋の「ご近所づきあい」
3 1歳児がいるのが当たり前の暮らし
Ⅱ 「暮らしの保育」の子どもの育ちと大人のまなざし
第3章 「子ども理解」から「子どもへのまなざし」へ――子どもは理解の対象でしょうか?
1 「子ども理解」への違和感
2 子どものことは、子どもがよく知っている
3 「直接理解」より「間接理解」
4 少し先と前の自分と重ね合わせて実感的にお互いを知っていく
5 子どもが大人をどう見ているかを知る
第4章 発達論的「理解」から実感的「理解」へ――子どもは手持ちの力で今を精一杯生きている
1 発達保障:異年齢保育は異年齢でも同年齢でも育つお得な保育
2 発達課題:「やりたくなった時がやり時(どき)」
3 目の前の子どもたちの姿から「実感として」発達を理解する
4 「どんな姿もその子」と多面的に見ます
5 異年齢保育(暮らしの保育)の発達論を
第5章 変化する大人のまなざし――「知る」「気にかける」「拾う」「距離感」
1 子どもを「理解する」ではなく「知る」
2 子どもの声は「聴く」より「拾う」
3 「わかろうとする」よりも「気にかける」
4 「気にかける」とは「ちょっと知っている」「作業しながら見ておく」
5 「困ったら言ってきてね。それまでは好きにしていいよ」という距離感
Ⅲ 「暮らしの保育」の構えと振る舞い
第6章 育ちの基盤としての「形成」
1 子どもは大人の暮らしの傍らで育つ
2 子ども同士「見よう見まね」で育ち合う
3 「教育の意図性」より「暮らしの必然性」「結果としての育ち」
4 「暮らしの保育」と「不適切保育」の問題
第7章 大人の構えと振る舞い――「願いをいったん横に置く」「重ねる、半身で暮らす」
1 「差」と「幅」と「気分」を認めて「時間帯」で保育する
2 一呼吸置く・願いを横に置く・間合いをはかる
3 学校的「話し合い」から村の寄り合い的な「話し込み」へ
第8章 大人同士の付き合いとコミュニティ――暮らしの保育に「先生」はいません
1 先生とは呼びません――名前や愛称で呼び合う間柄
2 保育園は「職場」であると同時に「暮らしの場」
3 保護者との間柄――一人の人間として、対等な子育てパートナー
第9章 過疎地の小規模・異年齢保育の魅力――地域も元気にする「屋根のない保育園」
1 小規模・少人数の保育は理想的な保育条件
2 条件的異年齢保育から自然体の異年齢保育へ
3 異世代交流とセットの「混ぜこぜ社会」「混ぜこぜ保育」
終章 「暮らしの保育」――まとめと検討課題
1 異年齢保育の先に見えてきた「暮らしの保育」
2 「暮らしの保育」の検討課題
3 「人間模様スケッチ」の提案(紹介)
4 「暮らしの保育」の発達論構築のために
【引用・参考文献】
寄稿1 「暮らしの保育」の夜明け 小山逸子
1 待ち望んでいた出版――異年齢保育では語りきれない「暮らしの保育」
2 「暮らしの保育」は、地域あってのものです
3 きたの保育園の「暮らしの保育」への道のり
4 未知の世界を共に創りあってきた土台は話し合いと学習でした
「暮らしの保育」をさらに深めるために――小山さんの「寄稿」を受けて〈宮里六郎〉
寄稿2 異年齢保育の背景と年齢別保育との関連 渡邉保博
1 保育・幼児教育における年齢別クラス編成をめぐって
2 年齢意識と今日の保育・幼児教育の問題
3 年齢別保育と異年齢保育との関連
著者の略歴
宮里 六郎(みやさと ろくろう)
1955年、鹿児島県種子島生まれ。中央大学文学教育学科卒業、東京学芸大学大学院教育学研究科修士課程修了。2020年年熊本学園大学社会福祉学部子ども家庭福祉学科退職、現在熊本学園大学名誉教授。専門:保育学。熊本異年齢保育研究会代表、全国保育問題研究会異年齢保育分科会運営委員。
主な著書:『里山の保育―過疎地が輝くもう一つの保育』(編著、2020年、ひとなる書房)『「子どもを真ん中に」を疑う―これからの保育と子ども家庭福祉』(単著、2014年、かもがわ出版)『保育に生かす実践記録―書く、話す、深める」(共著、2006年、かもがわ出版)『「荒れる子」「キレル子」と保育・子育て―乳幼児期の育ちと大人のかかわり」』(単著、かもがわ出版、2001年)
●寄稿
小山 逸子(こやま いつこ)元きたの保育園園長
「『ずーっと居たくなる暮らし』を求めて」『季刊保育問題研究』全国保育問題研究協議会編集委員会編、319号、新読書社、2023年他
渡邉 保博(わたなべ やすひろ)元佛教大学教授、静岡大学名誉教授
『「寂しい人のいない」保育園づくりと生活保育の探究:学校との関係を問い続けたある保育園の実践史に学ぶ』新読書社、2023年他
読者からの声
実践から立ち上がる「暮らしの中の育ち」とは |愛知学院大学・黒澤ひとみ
「生活」と「暮らし」をめぐる大切な気づき|宮城教育大学副学長・佐藤哲也
「暮らし」と「保育」は学童保育の原点であり、これからの道しるべ|宮城県学童保育緊急支援プロジェクト代表・池川尚美
読んでみて、心が震えた|常磐会学園大学・白川晴美
たくさんの示唆をもたらしてくれる|大東文化大学・中村清二
本書で描かれるのは、3〜5歳や1〜5歳の異年齢保育、また、地域や多世代交流も含めたなかで営まれる保育の実践と理論です。子どもたちは、日々の暮らしの中で大人や子ども同士で見よう見まねしながら、自分らしく育っていく。この自然なプロセスを見守り、気にかけ、大切にすることが、本書の核です。社会が「大人になる準備」を急ぎすぎるあまり、この「結果としての育ち」が置き去りにされている現状。本書は、そんな今の社会に一石を投じ、「今を丁寧に生きること」の意義を、問いかけています。
「子どものことは、子どもがよく知っている」「やりたくなった時がやり時」「『差』と『幅』と『気分』を認めて『時間帯』で保育する」
などなど……六郎さんと暮らしの保育を共に追求してきた園の方々の思いがつまった一冊です!(大阪青山大学 德留由貴)
新人の保育者、学ぶ余裕さえなく1日1日を必死に頑張っている中堅の保育者。当たり前と思ってそのスキルを磨いて根性論で乗り越えて積み上げた専門性。その保育者たちとこの本をつなぐ役割が必要なのでは。自分の言葉を持ち、伝えていく人、対話していく人が。
「暮らしの保育」の中に出てくる保育をメソッド的に真似るのではなく、考え方、心もち、子どもへの向き合い方などを、実践を通して、それぞれの場面で自分の言葉でその人たちへ橋渡しすること、あなたはどう思う? と聴く耳を持ち共に考えていくこと。そんなことが出来たらなと思いました。
保育の現場は想像以上に大変なことになっています。もっと悲しいのは、それを国も行政も気づいてないように感じてしまうことです。この保育論が一人でも多くの人の心に届きますように。良い本の出会いをありがとうございました。
最後になりますが、暮らしの保育を支えるのが、本来あるべき、乳幼児の保育ー広い意味での人間形成、教育的営みではないかと、思います。宮里先生の問題提起は、深いと痛感します。ひとことの思いを追加すると、ー学校モデルの年齢別とは違うーというところが、掘り下げて理解したいです。暮らしの保育が、学校を含めて、原点ではないかと。(白梅学園大学元学長 近藤幹生)